記事概要 令和6年度の東京都公立学校教員採用試験{令和6年度東京都公立学校教員採用候補者選考 (7年度採用)}の教職教養の問題解説をしていきます。けれど、間違った解説もあるかもしれませんので、鵜呑みするのは避けたほうがいいと思います。なお、間違った解説につきましては、発見次第、私Garudaに教えていただけると幸いです。
参考
教職教養の問題はこちら
https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/recruit/exam_r7/mondai00.pdf
教職教養問題の答えはこちら
https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/recruit/exam_r7/seito00.pdf
- 問1 教育基本法の条文として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問2 教育課程の編成や実施に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問3 学校において備えなければならない表簿に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の 1~5のうちのどれか。
- 問4 公立学校の教職員の採用又は任用等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問5 教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問6 教育職員の免許に関する記述として、教育職員免許法に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問7 教育公務員の研修に関する記述として、教育公務員特例法に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問8 地方教育行政に関する記述として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問9 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する記述として、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問10 西洋の教育史に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問11 イエナ・プランに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問12 次の記述は、「教育の情報化に関する手引(追補版)」(文部科学省令和2年6月)に示された、「教科等の指導におけるICTの活用」の「ICTを効果的に活用した学習場面の分類例」の「学習場面の分類に当たって」である。記述中の空欄ア~ウに当てはまる語句の組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
- 問13 次の記述ア・イは、それぞれ「生徒指導提要」(文部科学省 令和4年12月)の「生徒指導の基本的な進め方」の「生徒指導の基礎」の「生徒指導の意義」の「生徒指導の実践上の視点」に示された、下のA~Dのいずれかの内容に関するものである。ア・イと、A~Dとの組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
- 問14 不登校対策に関する記述として、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(文部科学省令和5年3月)に照らして適切でないものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問15 特別支援教育に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問16 「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 平成20年3月)に示された、「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問17 生命(いのち)の安全教育に関する記述として、「『生命(いのち)の安全教育』指導の手引き」(内閣府・文部科学省 令和3年4月)に照らして適切でないものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問18 心理学に携わった人物に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問19 パーソナリティ特性のビッグ・ファイブに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問20 動機づけに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問21 評価に誤差を与える要因に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問22 次の記述ア~ウは、集団の測定に関するものであり、ア~ウには、それぞれ下のA~Cのいずれかが当てはまる。ア~ウと、A~Cとの組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
- 問23 「令和5年度 文部科学白書」(文部科学省 令和6年8月)に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問24 「東京都教育振興基本計画 東京都教育ビジョン(第5次)」(東京都教育委員会 令和6年3月)に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 問25 学習指導要領総則に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
問1 教育基本法の条文として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
3 学問の自由は、これを保障する。
4 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
5 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
答えは ② です(教育基本法 第4条第1項)
解説 教育基本法に関しては条文の暗記度が得点に直結します。特に第1〜第5条あたりは、条文がそのまま出題されやすいので丸暗記を推奨します。
選択肢の解説
1 宗教的中立の規定ですが、文言が教育基本法第15条と異なり、「国及びその機関」だけではなく公立学校も含まれます。
2 正解。教育基本法第4条第1項そのままの記述です。
3 「学問の自由」は憲法第23条の規定で、教育基本法の条文ではありません。
4 義務教育妨害の禁止は学校教育法第16条の規定です。
5 就学援助は学校教育法第19条に規定されますが、記述の文言や趣旨が条文と異なっています。
問2 教育課程の編成や実施に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 小学校及び中学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合であっても、特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。
2 小学校及び中学校において、日本語に通じない児童・生徒のうち、当該児童・生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の教育課程によることができる。
3 文部科学大臣は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
4 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに外国語活動によって編成するものとする。
5 小学校においては、必要がある場合であっても、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができない。
答えは ② です(学校教育法施行規則 第56条の7)
解説 「特別の教育課程」というワードは、不登校児や日本語指導、病弱児で頻出します。対象と条件を整理して覚えましょう。
選択肢の解説
1 日本語指導や病弱児等に対して特別教育課程を編成することは可能ですので誤り。
2 正解。日本語に通じない児童・生徒には、文科大臣定めにより特別の教育課程で指導可能。
3 卒業証書を授与するのは校長であり、文科大臣ではありません。
4 中学校の教育課程に「外国語活動」は含まれません(外国語活動は小学校)。
5 小学校では必要に応じて合科的・関連的な指導が可能ですので、「できない」は誤り。
問3 学校において備えなければならない表簿に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の 1~5のうちのどれか。
1 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。
2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、原本を進学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。その保存期間は、二十年間とする。
4 指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、五年間とする。
5 校長は、児童等が転学した場合であっても、その作成に係る当該児童等の健康診断票を転学先の校長に送付する必要はない。
答えは ① です(学校教育法施行規則 第28条)
解説 保存期間(5年・20年)は鉄板問題。数字を変えて出すひっかけに注意が必要です。
選択肢の解説
1 正解。校長には在学児童等の指導要録を作成する義務があります。
2 指導要録の原本ではなく、抄本・写しを送ります。転学時でも規定は同じですので、「進学」と限定すると誤り。
3 出席簿の保存期間は5年であり、20年ではありません。
4 学籍に関する記録は20年保存ですが、「5年」としているため誤り。
5 健康診断票も転学時に送付する必要があります。
問4 公立学校の教職員の採用又は任用等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、幼保連携型認定こども園を除く、大学附置の学校以外の公立学校にあっては地方公共団体の長が行う。
2 免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者は、校長又は教員となることができない。
3 公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
4 公務員の職は、一般職と特別職とに分けられており、教育公務員のうち常勤の職員は一般職であるが、校長及び教育委員会の専門的教育職員は特別職である。
5 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満五年とする。
答えは ② です(教育公務員特例法 第5条)
解説 数字系(採用条件期間・休職年限など)は混同しやすいので表にまとめて覚えるとミスを防げます。
選択肢の解説
1 採用権は教育委員会にあり、地方公共団体の長ではありません。
2 正解。免許状取上げから3年未満は校長・教員になれません。
3 条件付採用期間は1年間で、6か月ではありません。
4 校長も一般職の教育公務員であり、特別職ではありません。
5 結核性疾患の休職期間は3年で、5年ではありません。
問5 教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することはできない。
2 教育公務員は、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないが、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすることについては認められている。
3 教育公務員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
4 幼保連携型認定こども園を除く公立学校の教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、地方公共団体の長の許可を受けなければならない。
5 教育公務員は、公選による公職の候補者となることができる。
答えは ③ です(地方公務員法 第32条)
解説 服務規律は「兼職条件」「争議行為禁止」「職務命令への服従」をセットで覚えるのがポイントです。
選択肢の解説
1 任命権者が認めれば兼職可能なので、「できない」とするのは誤り。
2 争議行為(ストライキ等)は全面禁止されています。
3 正解。法令や上司の職務命令に従う義務を明確にした規定です。
4 証人等として職務上の秘密を発表する場合の許可要件と混同しています。
5 公選公職の候補者になるには休職等が必要で、自由に立候補できません。
問6 教育職員の免許に関する記述として、教育職員免許法に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 普通免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。
2 普通免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 特別免許状は、その免許状を授与したときから三年間のみ効力を有し、かつ、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
4 教育職員で、その有する相当の免許状が一種免許状であるものは、相当の二種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
5 免許状を有する者が、公立学校の教員であって分限免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失うが、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失わない。
答えは ① です(教育職員免許法 第4条)
解説 免許状関係は「種類・効力・有効期間・授与権者」が鉄板テーマです。普通免許状は都道府県教育委員会が授与します。
選択肢の解説
1 正解。普通免許状は都道府県の教育委員会が授与します。
2 普通免許状は全国で有効で、授与した都道府県に限定されるものではありません。
3 特別免許状は授与から3年有効ですが、全国で効力があります。
4 一種免許状保持者であれば、二種免許状を受ける努力義務はありません。
5 分限免職だけではなく、懲戒免職を受けた場合も免許状は失効します。
問7 教育公務員の研修に関する記述として、教育公務員特例法に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、その採用の日から二年間の初任者研修を実施しなければならない。
3 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けることなく、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 教育公務員は、文部科学大臣の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
5 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童等に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、三年を超えない範囲内で、指導改善研修を実施しなければならない。
答えは ① です(教育公務員特例法 第21条)
解説 教育公務員の研修では、「絶えず研究と修養に努める」ことが基本です。初任者研修・指導改善研修・長期研修の条件も押さえておきましょう。
選択肢の解説
1 正解。教育公務員は職責遂行のため、絶えず研究と修養に努める義務があります。
2 初任者研修は1年間です(2年間ではない)。
3 勤務場所を離れる際は本属長の承認が必要です。
4 長期研修は文科大臣ではなく任命権者等の定めによります。
5 指導改善研修は1年以内であり、3年ではありません。
問8 地方教育行政に関する記述として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもって組織し、教育長及び委員は、再任されることができない。
2 総合教育会議は、教育長が招集する。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の二分の一以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
5 地方公共団体の長は、教育委員会の委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれないようにしなければならない。
答えは ③ です(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第30条)
解説 地方教育行政では、教育長・教育委員・総合教育会議の役割を整理することが重要です。特に「大綱」や「会議の公開条件」が頻出です。
選択肢の解説
1 教育長・委員は再任可能です。
2 総合教育会議は地方公共団体の長が招集します。
3 正解。大綱を定め又は変更した場合、速やかに公表する必要があります。
4 会議は原則公開ですが、非公開の決議要件は記述と異なります。
5 委員には保護者を含めるよう配慮します。
問9 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する記述として、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果において犯罪があると認めるときは、直ちに、児童相談所に通報しなければならない。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を講ずるものとするが、当該学校に在籍する教育職員等に対する定期的な調査を講ずる必要はない。
3 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる公務員は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒性暴力等を受けた児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援は行うが、当該児童生徒等の保護者に対する支援は行わない。
答えは ③ です(教育職員等による児童生徒性暴力等防止法 第7条)
解説 性暴力防止法は令和の新しい法律で、相談対応義務や免許失効者データベースなど、実務的要素が多く出題されます。
選択肢の解説
1 犯罪が認められる場合は、児相ではなく警察等に通報。
2 教職員等に対する調査も必要。
3 正解。犯罪があると思われる場合は刑事訴訟法に基づき告発義務があります。
4 データベース整備は国が行うもので、都道府県教委単独の義務ではありません。
5 保護者への支援も行う必要があります。
問10 西洋の教育史に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 コンドルセは、ヘルバルトの考えた四段階教授法を、予備、提示、比較、総括、応用という五段階教授法に発展させた。
2 マンは、自らが経営するニューラナークの紡績工場内に性格形成学院という教育施設を付設し、教育を無償で行った。
3 オーエンは、教育への権利は、全ての人間が生来もっている絶対的な自然権であるとし、無償の義務教育制度を提唱し、政治的・宗教的中立性に基づくコモン・スクールを構想した。
4 ラインは、「公教育の全般的組織に関する報告および法案」を議会へ提出した。また、公教育は国民に対する社会の義務であるとした。
5 ロックは、人間は生得的な観念はもたずにタブラ・ラサの状態で生まれ、経験の中で様々な観念を学んでいくことを主張した。
答えは ⑤ です(ロックの経験論)
解説 教育史は人名と業績をセットで覚えるのが基本です。特にロック、ルソー、ペスタロッチ、オーエン、マンなどは頻出される人物です。
選択肢の解説
1 五段階教授法はラインが提唱。コンドルセではない。
2 ニューラナークでの活動はオーエンの業績。
3 コモン・スクールを提唱したのはマン。
4 公教育の全般的組織報告を提出したのはコンドルセ。
5 正解。ロックは、人間は生得観念を持たず、経験によって形成されると主張(タブラ・ラサ説)。
問11 イエナ・プランに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 学習者が学習課題を見出し、その解決を目指し能動的に学習を展開する学習法である。理論的背景として、経験を積み重ね、経験を再構成していくことによって成長していくというデューイの反省的思考がある。
2 自発性に基づく目標設定、具体的活動の計画、計画の遂行、判断の四つの段階から構成される教育実践である。
3 自由と協同を基本原理とし、子供たちはアサインメントと呼ばれる1か月の学習を教師と相談して契約し、個別に学習を進めるものである。
4 学年学級制を解体して、基幹集団を編成し、対話、作業、遊戯、行事という四つの学習の基本形態で実践されるものである。
5 教育内容を、学習進度の個別化を図るコモン・エッセンシャルズと、集団活動を重視した集団的・創造的活動とに区分している。
答えは ④ です(イエナ・プラン)
解説 イエナ・プランは「学年学級制を解体し、4つの学習形態(対話・作業・遊戯・行事)」がキーワード。日本でもオルタナティブ教育として注目されています。
選択肢の解説
1 問題解決学習(デューイ)に関する記述であり、イエナ・プランではありません。
2 モリソン・プランの説明です。
3 ドルトンプランの説明です。
4 正解。学年学級制を解体し、基幹集団と4つの学習形態で実践するのが特徴。
5 ウィネトカ・プランの説明です。
問12 次の記述は、「教育の情報化に関する手引(追補版)」(文部科学省令和2年6月)に示された、「教科等の指導におけるICTの活用」の「ICTを効果的に活用した学習場面の分類例」の「学習場面の分類に当たって」である。記述中の空欄ア~ウに当てはまる語句の組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
※ A1は教師による教材の提示のことである。
※ B1は個に応じた学習、B2は調査活動、B3は思考を深める学習のことである。
※ C1は発表や話合い、C2は協働での意見整理のことである。
ア イ ウ
1 一斉学習 協働学習 情報活用能力
2 一斉学習 協働学習 問題発見・解決能力
3 一斉学習 協働学習 言語能力
4 協働学習 一斉学習 情報活用能力
5 協働学習 一斉学習 問題発見・解決能力
答えは ① です(ICT活用分類)
解説 ICTの分類は「ア=一斉学習」「イ=協働学習」「ウ=情報活用能力」の並びを覚えるのがポイント。単語の入れ替えが頻出です。
選択肢の解説
1 正解。ア=一斉学習、イ=協働学習、ウ=情報活用能力。
2 ウは情報活用能力が正しいので誤り。
3 ウは言語能力ではなく情報活用能力。
4 アは一斉学習が正しい。
5 アは一斉学習が正しい。
問13 次の記述ア・イは、それぞれ「生徒指導提要」(文部科学省 令和4年12月)の「生徒指導の基本的な進め方」の「生徒指導の基礎」の「生徒指導の意義」の「生徒指導の実践上の視点」に示された、下のA~Dのいずれかの内容に関するものである。ア・イと、A~Dとの組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
ア 児童生徒の教育活動の大半は、集団一斉型か小集団型で展開されます。そのため、集団に個が埋没してしまう危険性があります。そうならないようにするには、学校生活のあらゆる場面で、「自分も一人の人間として大切にされている」という自己存在感を、児童生徒が実感することが大切です。また、ありのままの自分を肯定的に捉える自己肯定感や、他者のために役立った、認められたという自己有用感を育むことも極めて重要です。
イ 児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・ホームルームで安全かつ安心して教育を受けられるように配慮する必要があります。他者の人格や人権をおとしめる言動、いじめ、暴力行為などは、決して許されるものではありません。お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授業や学校生活が送れるような風土を、教職員の支援の下で、児童生徒自らがつくり上げるようにすることが大切です。そのためには、教職員による児童生徒への配慮に欠けた言動、暴言や体罰等が許されないことは言うまでもありません。
A 自己存在感の感受
B 共感的な人間関係の育成
C 自己決定の場の提供
D 安全・安心な風土の醸成
1 ア-A イ-B
2 ア-A イ-D
3 ア-B イ-C
4 ア-B イ-D
5 ア-C イ-D
答えは② です(生徒指導提要)
解説 視点ごとのキーワードを押さえると対応しやすい。「自己存在感=A」「安全・安心な風土=D」が頻出セットです。
選択肢の解説
1 イはDが正しいので誤り。
2 正解。ア=A(自己存在感)、イ=D(安全・安心な風土)。
3 アはAであるべき。
4 アはAであるべき。
5 アはAであるべき。
問14 不登校対策に関する記述として、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(文部科学省令和5年3月)に照らして適切でないものは、次の1~5のうちのどれか。
1 「不登校の児童生徒への支援に加え、その保護者が必要とする情報を提供するとともに、子供たちが様々な学びの場や居場所につながることができるよう、地域の拠点としての教育支援センターに求められる機能や役割を明確化します。」とされている。
2 「希望すれば、1人1台端末を活用して、自宅をはじめとする多様な場を在籍校とつなぎ、オンライン指導やテスト等も受けられ、その結果が成績に反映されるようにします。」とされている。
3 「SOSをキャッチした後に、教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護教諭、学校医等が専門性を発揮して連携し、最適な支援につなげることができるよう、スクリーニング会議やケース会議の開催方法・支援方法を確立します。」とされている。
4 「自分のクラスに入りづらい児童生徒が、落ち着いた空間の中で自分に合ったペースで学習・生活できる環境を学校内に設置します。」とされている。
5 「公立学校のノウハウを取り入れた不登校の児童生徒への支援が行えるよう、業務委託や人事交流等を通して、NPOやフリースクール等との連携を強化します。」とされている。
答えは⑤ です(COCOLOプラン)
解説 不登校対策では、オンライン活用、学校内の別室設置、地域連携がキーワード。細部の可否を変えてくるひっかけに注意。
選択肢の解説
1 正しい記述。
2 正しい記述。
3 正しい記述。
4 正しい記述。
5 正解(不適切な記述)。保護者支援も含めて行う必要があるため、「行わない」は誤り。
問15 特別支援教育に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 特別な支援を必要とする児童・生徒の実態の把握については、学校が実態の把握に努め、児童・生徒の存在や状態を確かめることが必要であり、実態の把握は、学級担任だけに固定する。
2 特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などの役割を担う。
3 養護教諭は、全校的な支援体制を確立し、発達障害を含む障害のある児童・生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内委員会を設置する。
4 個別の教育支援計画は、個々の児童・生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるものであり、教育課程を具体化し、一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確にして、きめ細やかに指導するために作成される短期的な計画のことである。
5 個別の指導計画は、障害のある児童・生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とし、学校が中心となって医療・福祉等の関係機関と連携しながら作成する長期的な計画のことである。
答えは② です(特別支援教育)
解説 特別支援教育では「特別支援教育コーディネーターの役割」「個別の教育支援計画(長期)と個別の指導計画(短期)」の違いを必ず押さえましょう。
選択肢の解説
1 実態把握は学級担任に限りません。全教員・関係機関で行います。
2 正解。コーディネーターの役割として、校内研修企画や関係機関調整などが挙げられます。
3 養護教諭ではなく校長の下で校内委員会を設置します。
4 個別の指導計画は短期的な計画ではなく、誤り。
5 個別の教育支援計画が長期的計画であり、逆になっているため誤り。
問16 「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」(人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 平成20年3月)に示された、「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律では、「人権教育とは、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるようにすること」と定義している。
2 人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向的な感覚である。
3 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「知識的側面」は、人権に関する知的理解に深く関わるものであり、自由、責任、正義、個人の尊厳、権利、義務などの諸概念についての知識、人権の歴史や現状についての知識、国内法や国際法等々に関する知識、多様性に対する肯定的評価等が含まれる。
4 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「価値的・態度的側面」は、人権感覚に深く関わるものであり、人権教育が育成を目指す価値や態度には、人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、責任感、正義や自由の実現のために活動しようとする意欲、偏見や差別を見きわめる技能が含まれる。
5 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「技能的側面」は、人権感覚に深く関わるものであり、人権教育が育成を目指す技能には、コミュニケーション技能、合理的・分析的に思考する技能、自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知識、相違を認めて受容できるための諸技能、協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、責任を負う技能が含まれる。
答えは② です(人権教育の指導方法等の在り方)
解説 人権教育は「知識的側面」「価値的・態度的側面」「技能的側面」を区別して覚えるのがコツ。定義部分も出やすい傾向です。
選択肢の解説
1 人権教育は法律で定義されたものではありません。記述が誤っています。
2 正解。人権感覚の定義とするのが正しい記述です。
3 「知識的側面」の説明としては正解ですが、設問では別の側面との混同を狙っています。
4 価値的・態度的側面の説明として正しいものですが、問いには該当しません。
5 技能的側面の説明として正しい内容ですが、問いには該当しません。
問17 生命(いのち)の安全教育に関する記述として、「『生命(いのち)の安全教育』指導の手引き」(内閣府・文部科学省 令和3年4月)に照らして適切でないものは、次の1~5のうちのどれか。
1 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要がある。
2 生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付け、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにする。
3 高校の発達段階においては、性暴力に関する現状を理解し、正しい知識を持つことができるようにし、性暴力が起きないようにするために自ら考え行動しようとする態度や、性暴力が起きたとき等に適切に対応する力を身に付けることができるようにする。
4 児童生徒から相談を受けた場合には、児童生徒から被害開示を受けた教職員が怒りや動揺を見せると、被害児童生徒は共感を得たことに安心して落ち着いて話をすることができるため、教職員は感情的に対応をするよう留意する。
5 指導に当たっては、家庭で、性暴力被害、身体的虐待や心理的虐待、ネグレクトの被害を含む被害経験がある児童生徒は、「自分の体も相手の体も大切」等の内容を理解、実践できない可能性がある点に配慮する必要がある。
答えは④ です(生命の安全教育)
解説 性暴力防止教育では発達段階ごとの指導内容と、相談時の教職員の態度(冷静・感情を抑える)が頻出ポイントです。
選択肢の解説
1 正しい記述。
2 正しい記述。
3 正しい記述。
4 正解(不適切な記述)。教職員には冷静に対応する必要があり、感情的対応は誤りです。
5 正しい記述。
問18 心理学に携わった人物に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 ウェクスラーは、1911年に自由精神分析協会を設立した。劣等感を克服したいということが、人の行動の原動力であると考えた。
2 ジェームズは、1939年に、成人用の知能検査を考案し、発表した。この検査は言語性検査と動作性検査の二領域で構成される。
3 アドラーは、1950年に、「幼児期と社会」を著した。心理社会的発達理論を展開し、八つのライフサイクルにおける青年期の発達課題として、アイデンティティという概念を用いた。
4 エリクソンは、1890年に「心理学原理」を出版した。身体的な反応は刺激を知覚した後に起こって、その反応に対して抱く感じが情動であると主張した。
5 エビングハウスは、1885年に「記憶について」を発表した。忘却は、学習直後の短時間では急激に起こり、その後の過程では徐々に進行することを忘却曲線に示した。
答えは⑤ です(エビングハウスの忘却曲線)
解説 心理学に関しては人物名+代表的業績をセットで覚えること。年代や著書名も組み合わせで出題されます。
選択肢の解説
1 劣等感の克服を説いたのはアドラーです。
2 成人用知能検査(WAIS)はウェクスラーで、1939年発表は正しいが人名が逆。
3 心理社会的発達理論とアイデンティティはエリクソンの業績。
4 「心理学原理」と情動説はジェームズの業績。
5 正解。エビングハウスは1885年に「記憶について」を発表し、忘却曲線を示しました。
問19 パーソナリティ特性のビッグ・ファイブに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 創造性、好奇心の高さを表す因子は、外向性である。
2 慎重さ、まじめさを表す因子は、誠実性である。
3 社交性や物事への積極性を表す因子は、神経症傾向である。
4 共感性、寛容性の高さを表す因子は、開放性である。
5 不安や緊張の高さ、傷つきやすさを表す因子は、調和性である。
答えは②です(ビッグ・ファイブ)
解説 ビッグ・ファイブは「外向性・誠実性・開放性・調和性(協調性)・神経症傾向」の5要素を意味とセットで覚えること。
選択肢の解説
1 創造性・好奇心は開放性です。
2 正解。慎重さ・まじめさは誠実性です。
3 社交性・積極性は外向性です。
4 共感性・寛容性は調和性(協調性)です。
5 不安や緊張の高さは神経症傾向です。
問20 動機づけに関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 学習性無力感とは、ある課題に直面したときに、期待された結果を自分の知識や技能などによって得ることができるという自信や信念のことである。
2 ホーソン効果とは、注目され観察されているということが、成績や生産性の向上に影響することである。
3 自己効力感とは、課題を回避しようとする行動をとってもその結果が得られない状態に長期間置かれると、無気力な状態に陥ってしまい、課題を回避しようとする努力すら行わなくなってしまう現象のことである。
4 アンダーマイニング効果とは、自発的な活動に対し褒めのような言語的報酬を与えると、内発的動機づけが高まることである。
5 エンハンシング効果とは、自発的な活動に対し外的報酬を与えると、内発的動機づけが低下することである。
答えは ② です(ホーソン効果)
解説 動機づけ理論は効果名と現象を正確にリンクさせるのが重要。特に学習性無力感・自己効力感・アンダーマイニング効果は混同されやすい内容です。
選択肢の解説
1 学習性無力感の説明が自己効力感になっていて誤り。
2 正解。ホーソン効果は注目・観察されることで成績や生産性が向上する現象。
3 これは学習性無力感の説明です。
4 アンダーマイニング効果は外的報酬で内発的動機づけが低下する現象であり、誤り。
5 エンハンシング効果は外的報酬で内発的動機づけが高まる現象。
問21 評価に誤差を与える要因に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 寛容効果は、評価者が、自分を中心に考え、被評価者を自分と対比して評価してしまうことである。
2 中心化傾向は、自分と相性がよい相手の言動を甘く判断し、実際よりも上位の段階に評価する傾向のことである。
3 対比誤差は、第一印象に基づき行動全体を評価する傾向のことである。
4 ハロー効果は、一部のよい側面に注目すると、全体的によい評価をしてしまい、逆に、いくつかの悪い側面に注目すると、総じて悪い評価をしてしまう現象である。
5 初頭効果は、極端に高い評価や低い評価を避けた結果、真ん中の値ばかりになり、評価に差がつかなくなってしまうことである。
答えは④です(評価の誤差要因)
解説 評価誤差の名称と定義はひっかけの定番です。特にハロー効果・中心化傾向・対比誤差は混同しやすいので、用語カード化を推奨します。
選択肢の解説
1 寛容効果は「甘く評価する傾向」のことであり、自分と比較するのは対比誤差です。
2 中心化傾向は評価が真ん中に集中する現象です。「相性が良いから高評価」は寛容効果。
3 対比誤差は自分や他者との比較により評価が変わる現象です。初頭効果と混同しています。
4 正解。ハロー効果は一部の印象が全体評価に影響する現象です。
5 初頭効果ではなく、これは中心化傾向の説明です。
問22 次の記述ア~ウは、集団の測定に関するものであり、ア~ウには、それぞれ下のA~Cのいずれかが当てはまる。ア~ウと、A~Cとの組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
ア 質問紙の形式で具体的な行動やパーソナリティ傾向を例示し、該当する級友の名前を記入するもので、子供同士の人物評価を知ることができる。
イ 集団の成員間での選択および排斥の感情関係を測定・分析することによって、集団の構造を明らかにすることを目的としている。
ウ 学級満足度尺度と学校生活意欲尺度で構成され、児童・生徒の学級生活の満足度を把握することができる。
A ソシオメトリック・テスト
B Q-U
C ゲス・フー・テスト
1 ア-A イ-B ウ-C
2 ア-A イ-C ウ-B
3 ア-B イ-A ウ-C
4 ア-C イ-A ウ-B
5 ア-C イ-B ウ-A
答えは④です(集団測定法)
解説 ゲス・フー、ソシオメトリック・テスト、Q-Uの特徴を混同しないよう整理。名称と目的を必ずセットで覚えましょう。ゲス・フーは、英単語の意味からもその内容は理解できるでしょう。
選択肢の解説
1 アはゲス・フー、イはソシオメトリック・テスト、ウはQ-Uなので誤り。
2 アはゲス・フー、イはソシオメトリック・テスト、ウはQ-Uなので誤り。
3 アはQ-Uではない。
4 正解。ア=ゲス・フー、イ=ソシオメトリック・テスト、ウ=Q-U。
5 アはゲス・フーではない。
問23 「令和5年度 文部科学白書」(文部科学省 令和6年8月)に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 理数教育を着実に実施するため、教員によって負担の大きい実験の準備・調整等の業務を軽減するための理科観察実験アシスタントの配置支援や、「理科教育振興法」に基づき、公・私立の小・中・高等学校等における観察・実験に係る実験用機器をはじめとした理科、算数・数学教育に使用する設備の計画的な整備を進めている。
2 「トビタテ!留学JAPAN」第2ステージ「新・日本代表プログラム」において小学校段階からの留学への支援を充実するなど、海外経験・留学支援に係る取組を促進し、令和5年度から5年間で4,000人を派遣していくとしている。
3 学校における安全教育や安全管理の充実に向けて、学校が危機管理マニュアルを作成・見直す際の参考資料「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を作成し、活用を促している。
4 国際教育到達度評価学会では、児童生徒の算数・数学と理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児童生徒の教育上の諸要因との関係を明らかにするため、小学校4年生、中学校2年生を対象として「生徒の学習到達度調査(PISA)」を4年ごとに実施している。
5 児童生徒が自分の心の状態に気付き、心の状態に影響する要因に目を向け、自分に合った方法で適切に対処することができるよう、日本学校保健会を通じて「心のバリアフリーノート」を作成・周知し、児童生徒の自身の健康を管理し改善する力の育成を図っている。
答えは①です(令和5年度文部科学白書)
解説 白書系は具体的事業名と内容をペアで覚えること。PISAやTIMSS、各種プロジェクトの目的を押さえると得点源になります。
選択肢の解説
1 正解。理科観察実験アシスタント配置や設備整備の記述は正しい。
2 小学校段階からの留学支援は示されていません。
3 「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」は安全管理マニュアルではない。
4 PISAは15歳対象であり、算数・数学・理科だけでなく読解力も対象。小4・中2対象はTIMSS。
5 心のバリアフリーノートは正しいが、白書の該当部分とは異なる。
問24 「東京都教育振興基本計画 東京都教育ビジョン(第5次)」(東京都教育委員会 令和6年3月)に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 「グローバルに活躍する人材を育成する教育」において、「異なる言語や文化を乗り越え関係を構築する力、新しい価値を創造する力の育成」という方向性を示し、子供たちが運動やスポーツとの多様な関わり方を通して、健康で活力に満ちた生活をデザインすることができるようになることを目指し、「TOKYO ACTIVE PLAN for students」の推進をするとしている。
2 「健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育」において、「生涯を通じて、たくましく生きるために必要な体力を育む教育の推進」という方向性を示し、児童・生徒が英語を使用する楽しさや必要性を体感でき、英語学習の意欲向上のきっかけづくりとなる実践的な学習を行うため、「TOKYO GLOBAL GATEWAY」の活用を促進するとしている。
3 「全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育」において、「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善の推進」という方向性を示し、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための効果的な指導方法の開発に向け、「個別最適な学びと、協働的な学び」を踏まえた実践的な研究・研修を推進し、その成果を幅広く全都へ発信・普及するとしている。
4 「豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態度を育む教育」において、「他者への思いやりなど、豊かな心を一人ひとりの子供たちに育む教育の推進」という方向性を示し、データ活用・分析等による授業の改善に向け、各種データを可視化、分析する教育ダッシュボードを順次導入し、学習ログ等を活用したエビデンスベースの指導を展開するとしている。
5 「Society5.0 時代を切り拓くイノベーション人材を育成する教育」において、「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代を生き抜く人材の育成」という方向性を示し、優れた授業実践を公開するとともに、「考え議論する道徳」の実現に向けた指導の在り方や工夫等について学ぶことができる「『特別の教科 道徳』授業力向上セミナー」を実施することで、教員の授業力向上を図るとしている。
答えは③です(東京都教育ビジョン)
解説 こんな問題は捨てていいでしょう。覚えるだけ時間の無駄です。
選択肢の解説
1 TOKYO ACTIVE PLANは健康・運動関連であり、グローバル人材育成ではありません。
2 TOKYO GLOBAL GATEWAYは英語体験施設であり、体力育成ではありません。
3 正解。「主体的・対話的で深い学び」実現に向け、個別最適と協働的学びを踏まえた研究・研修を推進。
4 データ活用や教育ダッシュボードは学力向上や授業改善の施策であり、「豊かな心」ではありません。
5 「考え議論する道徳」授業力向上セミナーはDX人材育成ではありません。
問25 学習指導要領総則に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 児童・生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、読書活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ることとされている。
2 教育課程の編成及び実施に当たっては、学校がその目的を達成するため、学校の実態のみに応じ、教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど、家庭や地域社会との連携及び協働を深めることとされている。
3 言語能力の育成を図るため、各学校において必要な言語環境を整えるとともに、理科を要としつつ各教科等の特質に応じて、児童・生徒の言語活動を充実することとされている。
4 各学校が行う学校評価については、教育課程の編成、実施、改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ、カリキュラム・マネジメントと関連付けることなく実施するよう留意するものとするとされている。
5 道徳教育の目標を踏まえ、道徳教育の全体計画を作成し、校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開することとされている。
答えは⑤です(学習指導要領総則)
解説 総則問題は「特定の教育(道徳・キャリア・言語)+方針+推進体制」がセットで狙われます。文言の入れ替えに注意。
選択肢解説
1 キャリア教育では、読書活動を要とするとは規定されていません。
2 学校の実態「のみ」に応じるのは誤り。地域や家庭との連携も必須。
3 言語能力育成の要は「国語」であり、「理科」ではない。
4 学校評価はカリキュラム・マネジメントと関連付けて行う。
5 正解。道徳教育は全体計画を作成し、推進教師を中心に全教師で展開する。

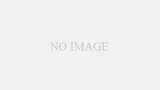
コメント