前回記事はこちら
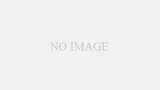
皇族は腫れ物
筑波大学附属高校の教員にとって、秋篠宮悠仁様のような皇族の生徒は扱いにくい存在だ。皇族は国民の注目を浴び、メディアや世論がその一挙手一投足を見張る。もし皇族の身になにかあれば、学校だけでなく、様々な方面の人間からバッシングを食らうことになる。
悠仁様が提携校進学制度で入学した際、「特別待遇」との声が上がり、教員は公平性を保つプレッシャーにさらされた。腫れ物に触るように接する必要が生じ、特別扱いを避けつつも、他の生徒と同じ基準で評価するのは困難だ。皇族の存在は教員に過剰な配慮を強いる一方、教育現場の自由度を奪う。筑波大学附属高校(筑附)のような進学校では、この緊張感が授業運営に影を落とす。特殊な存在であり、教員や学校の負担は否応なしに増える。
勉強は才能
勉強は才能である。筑波大学附属高等学校の偏差値は78程度で、ほとんどの生徒が筆記試験を突破して入学してくる、全国トップクラスの超進学校だ。学力のない子どもは足切りにあうので、入学してくる生徒のほとんどは天才で、生徒の学力のレベルが担保されている。首都圏の天才の中の天才だけが入学できるのが、名門、筑波大学附属高等学校である。
ほとんどの生徒が圧倒的な学力を備えているので、学校全体で高水準の教育を施すことができるし、生徒もハイレベルな授業についてくる。国立学校の教員は特殊で、人事異動はほとんどなく、学力の高い生徒を指導することになる。
悠仁様はトンボ研究で実績を上げ、それが推薦入学の根拠とされたが、学業全般での才能は未知数だ。むしろ、悠仁様が推薦を選んだことは、筆記試験での実力に限界があることを示唆する。
人材ピラミッドについてはこちら
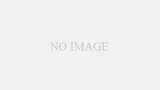
推薦入学と筆記試験入学の学力差
2022年、秋篠宮悠仁様が筑波大学附属高等学校に入学。お茶の水女子大学附属中学校との提携校進学制度において推薦による入学である。高校ではよくあることだが、推薦入試で入学してくる生徒は、筆記試験で入学してくる生徒より学力で劣ることがある。
秋篠宮悠仁様は推薦で筑波大学附属高等学校に進学したが、筆記試験で筑波大学附属高等学校に入学してきた生徒との学力差は尋常ではないものだったと容易に想定される。筑波大学附属高等学校では、推薦入学してくる生徒がほとんどいないので、異質な存在が1人だけいるような状況が生まれていただろう。
筑附の授業は進度が速く、東大を目指す生徒向けに設計されている。推薦組がこのペースについていけない場合、教員は指導に苦慮する。学力差が大きいと、クラス全体のレベル調整が難しくなり、教員の負担が増す。これは、公立学校におけるインクルーシブ教育に類似している。
インクルーシブ教育の一番の弊害
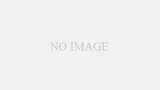
インクルーシブ教育は、すべての子どもたちが、障害の有無にかかわらず、同じ教室で学び、共に育つ機会を提供する教育アプローチである。公立学校でのインクルーシブ教育では、生徒によっては授業についていけず、進度の関係で教員は直接助言を与えるようなことがなかなかできず、教員も生徒もストレスがたまるというようなことが発生することがある。
もし悠仁様が学級の平均より学力が低い場合、教室はインクルーシブ教育の場と化す。インクルーシブ教育は、多様な能力を持つ生徒を同じ環境で学ばせる理念だが、進学校では現実的でない。筑附では高学力を前提に授業が進み、低学力の生徒がいるとペースが乱れる。教員は悠仁様を特別扱いせず、他の生徒と同等に扱うべきだが、学力差が大きければ個別対応が必要になる。これは時間と労力を奪い、一般入試組への指導が手薄になるリスクがある。皇族ゆえの注目度が加われば、教員は公平性と教育効果の間で板挟みに遭う。インクルーシブ教育は理想だが、学力格差が極端な場合、進学校の目的である進学実績が損なわれかねない。
インクルーシブ教育の一番の弊害は「普通の生徒が割を食う」ことである。倫理的な問題で、こういったことには声を上げるのが憚られるのが近年の風潮ではあるが、「筑波大学附属高等学校に皇族がいる」というだけでインクルーシブ教育のような状況が発生するのは、教員だけでなく生徒にとってもたまったもんじゃなかっただろう。
この続きはこちら
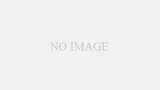

コメント