記事概要 昨今、首都圏では中学受験熱が高まり、中学受験を検討する小学生が増えている。学力において「トンビが鷹を産む」というような例はあるが、実際にこれはどんなことが起きているのか解説する。
前回記事はこちら
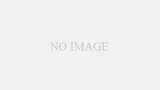
勉強は才能であり遺伝子は嘘をつかない
勉強ができるかどうかは、本人の努力だけでなく、才能に大きく依存している。才能の根源は遺伝子であり、遺伝子が持つ設計図がその人のポテンシャルを決定づける。
生まれつき記憶力や論理的思考力が優れている者は、たとえ同じ環境で学んだとしても、他の人々よりも遥かに高い成果を上げる。遺伝子は人間の可能性をある程度まで規定しており、それは努力では超えられない壁でもある。親が学力的に優れていれば、その子どもも優れた能力を受け継ぐことが多い。逆に、親が学力的に劣っていれば、その影響が子どもにも反映される可能性が高い。遺伝子は、嘘をつかないのだ。
学力面でトンビが鷹を産む例はある
しかしながら、学力において「トンビが鷹を産む」というような例が存在することも否定できない。親の学力が平均以下であっても、子どもが飛び抜けた才能を発揮するケースがある。この現象は、遺伝的な突然変異や、祖先の遺伝子が隔世遺伝して表出する可能性によると考えられる。
学力が高い子どもが親の期待以上の成果を出すことは、特に教育環境が整っている現代社会では注目される事例である。しかし、こうしたケースが例外的であることもまた事実だ。
果たしてその子どもは本当にトンビの子どもなのか
「トンビが鷹を産む」場合、その子どもが本当にトンビ(親)の子どもであるかどうかを疑問視する声もある。
学問的には、家系内で突然変異が起きる可能性がゼロではないが、それ以上に「托卵(たくらん)」の可能性が指摘されることもある。つまり、実際の父親や母親が別の人物である場合も考慮しなければならない。子どもの学力が親の予想をはるかに超える場合、その背景には遺伝の流れに異変が起きている可能性が否定できない。子どもの学力を研究について真理に到達したいのであれば、そもそもその子どもが本当に両親の子どもなのかの確認が不可欠である。
人類史において「托卵」は昔からたくさんあったこと
托卵とは、他者に自分の卵(子ども)を育てさせる現象を指す。動物界ではカッコウが有名だが、人間社会においても「托卵」は古くから存在していた。
封建社会や身分制度が強かった時代、特に貴族や王族の間では、血統を守るために「托卵」が行われるケースがあったとされる。DNA鑑定が未発達であった時代には、それを証明する術がなかったため、托卵の事実は歴史の中に埋もれている。現代社会でも、この現象が一定の割合で存在していると推測される。
無論、妻が夫に、「この子どもにあなたの遺伝子は含まれていない」とは言わないであろう。わざわざ離婚につながるようなことは誰もしない。
学習のデータを取るなら、まずDNA鑑定から
倫理的な問題はあるかもしれないが、親の学力と子どもの学力を計測するならば、DNA鑑定から始めないと意味はない。
親子関係が明確でなければ、学力と遺伝の相関性を正しく評価することはできない。遺伝子情報を正確に把握することで、「トンビが鷹を産む」という事例が、遺伝的背景によるものか、「托卵」によるものかを明確にすることができるだろう。科学技術の進歩を活用すれば、学力についての研究の精度が一段と向上し、才能の本質に迫ることが可能となる。
この続きはこちら
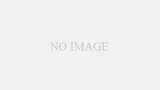

コメント