記事概要 昨今、首都圏では中学受験熱が高まり、中学受験を検討する小学生が増えている。中学受験ブームが弱者ビジネスになりつつあるという現実から考えて、今後未来の中学受験はどうなっていくのかを解説する。
前回記事はこちら
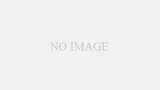
私立中学校受験には金がかかるが、そもそも金銭的に余裕がある家庭しか相手にしていないので、足切りができている
私立中学校受験では、塾の費用、模試代、教材費、受験料、さらには進学後の学費といった形で、多額の費用が発生する。そのため、そもそも金銭的に余裕のない家庭は参加できず、一定の「足切り」が自然に行われていると言える。
私立中学校は経済的に余裕のある層を主なターゲットに据えることができる。これにより、教育資源を金銭的な余裕がある家庭の子どもに集中させることが可能になり、経営リスクを低減している。結果として生徒を確保し続けられる限り、安定した収益を上げることができる。
中学受験することで子どもが賢くなったと保護者は思えるし、私立中学校は金を稼げるので、双方に利益があるような関係になる
中学受験を経て私立中学校に入学し、大学に進学することで、多くの親は「子どもが賢くなった」「良い教育環境に進んだ」と感じる。一方、私立中学校は入学金や授業料を安定的に得ることで収益を上げ、教育ビジネスとして成立する。
表面的には、親と学校の間に利益の一致があるように見える。しかし実際には、学力が大きく向上するケースは限定的であり、教育の本質的な価値が得られているかは疑問が残る。それでも、この「利益が一致しているように見える」構造が、中学受験市場の安定的な成長を支えている。
メディアは私立中学校受験を勧めるだろうが、ブームが去ったときに、偏差値が低い私立学校の中学部は人が集まらなくなる
メディアは、私立中学校受験を「子どもの未来への投資」として推奨することが多い。教育熱心な親たちは、こうした宣伝に乗せられ、中学受験を選択する。しかし、このブームが終焉を迎えたとき、偏差値が低い私立中学校は、生徒を確保するのが難しくなる。
実際、少子化が進む中、若者に金銭的な余裕がなくなり、中学受験ブームが沈静化すれば、多くの家庭が受験を避ける方向に動く可能性がある。そもそも中学受験は子どもの進学の選択肢の一つにすぎないだけで、義務教育が機能している限り、必ずしも私立中学校に進学する意味はない。
特に魅力的な教育プログラムを持たない中堅以下の私立学校は、生徒を確保できなくなり、経営に行き詰まるリスクが高まるだろう。
未来はどうなるか。馬鹿は教育の投資効果が薄いと気が付くのか。馬鹿は馬鹿のまま教育に投資をしていくのか。
中学受験ブームが持続するかは、親が「教育への投資効果」に気付くかどうかにかかっている。
教育の成果が必ずしも目に見える形で現れない場合、経済的に余裕のない層や冷静な判断をする層は、中学受験に費用をかける意味を疑い始める可能性がある。一方で、情報に流されやすい層や、「とりあえず周りと同じことをする」傾向のある層は、引き続き中学受験に投資を続けるだろう。
未来の選択肢は二つに分かれる。一つは、合理的に教育の本質を見極める家庭が増えることで、受験市場が縮小する方向。もう一つは、教育に対する幻想を捨てきれない層が市場を支え続ける方向である。いずれにせよ、教育業界はこの変化に適応しなければ生き残れないだろう。
この続きはこちら
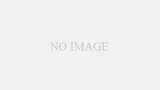

コメント