記事概要 現状では、学校教育には様々な課題があります。例えば、教員の労働時間はなかなか短くなりません。今回は、教員の過剰労働の一因は部活動であること、子どもへの悪影響や矛盾をなくすため、負担軽減が必要であることについて解説していきます。
前回記事はこちら
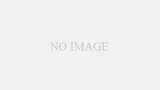
労働基準法と教員の労働時間
労働基準法では、「労働者は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはいけない」と明記されています。このルールは早ければ小学校6年生で学ぶ内容です。しかし、公立学校教員で週40時間労働を守られている例はほとんどありません。無償の残業が当たり前の環境にあり、特に運動系の部活動では、平日は授業後に練習を行い、土日祝日にも練習や試合があることが多々あります。部活動の顧問は、活動が終わるまで帰宅できません。さらに、土曜日に授業がある場合、どのように計算しても労働時間は40時間を超えます。これは明らかなルール違反であり、小学生でも理解できる問題です。
教員は子どもにとって身近な、大人の見本であるべきです。教員が子どもの憧れの存在であり続けることは、将来の教育者を育て、国の未来を支えるために重要です。また、親がいない子どもにとっては、教員が親のような存在となることも求められます。
教員の働き方が子どもに与える影響
教員が毎日残業する姿を見て、「大人は残業が当たり前」と子どもは感じるかもしれません。その結果、残業を美徳と捉え、社会に出てから過労で体を壊す、生産性や効率を追求せず、「職場に長く居座るほうが評価される」と考える若者が増える可能性が十分にあります。このような負の連鎖を断ち切るためには、教員が労働基準法に従った働き方を実践し、子どもに正しい労働観を示す必要があります。言葉では1日8時間労働と指導しながら、自らは10時間以上働くようでは、子どもに矛盾を感じさせてしまいます。
教育者としての責任と課題
言っていることとやっていることを教育者が矛盾させれば、子どもは失望し、教員の言葉に説得力がなくなります。平然と嘘をつく人間を、誰が信用するでしょうか。部活動が存在することで、教員は労働時間を超えた働きを余儀なくされ、その結果、子どもに誤ったメッセージを送ることになります。どれほど身を削って生徒のために働いても、それは子どもや社会、未来のためにはなりません。自らの自己満足のために教員として働く人間は教育者失格です。子どもの不幸につながります。部活動を含め、教員の負担を減らし、適正な働き方を実現することが必要です。
この続きはこちら
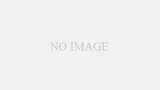

コメント