教員による女子児童・生徒の盗撮と、盗撮したデータを共有する教員グループの存在が世間を騒がせている。逮捕者の出た学校では、緊急保護者会が開かれたが、学校管理職からどのような説明があり、保護者からどのような意見が出されたかは不明なものの、問題の解決に至ったとは思われない。さらに言えば、教員に限った問題だろうか。
そもそも盗撮なる言葉は、カメラやその附属用品が進化し、また、カメラのデジタル化が主流となるにつれて目にするようになったと考える。写真機といえばフィルムカメラだった時代では、撮影できる枚数は限られていたため、シャッターは安易には切れなかった。また、フィルムの現像は自宅では難しく、写真の主な保存先はアルバムだった。さらに、写真(データ)を共有(入手)するには、ネガを焼き増ししてもらうしかなかった。古いスパイ映画で、事件の証拠となるネガを買い取ったり焼き捨てたりする場面を見たことがある。
デジタルカメラが現れ、写真の撮り直し、つまり、データの消去が可能になると、シャッターを切る、シャッターボタンを押すことに抵抗がなくなった。あれもこれも撮影することが一般的になった。携帯電話やスマートフォンに写真(撮影)機能が標準装備されると、誰もが写真家に変身し、手にした大量の写真(データ)の保存や交換が日常茶飯事となった。
インターネット上に、盗撮されたデータや盗撮の方法が紹介されていれば、犯罪行為と知りつつ、『できるかもしれない。やってみようかな』という思いを抱くかもしれない。そして、一度成功すると、歯止めが利かなくなるかもしれない。
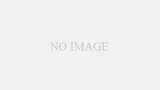
相手に迷惑をかけていない……盗撮
盗撮という、マイナスのイメージをもつ言葉が世間を騒がす前のこと、『どっきりカメラ』という人気のテレビ番組があった。一般人がさまざまな仕掛けやトリックに騙され、驚かされた様子を隠し取り、つまり、「盗撮」し、放送した番組だったが、批判や非難の対...
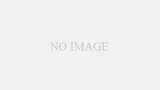
教員・警察官・自衛隊員による盗撮
教員や警察官や自衛隊員が引き起こす事件や不祥事に対する世間の視線は厳しい。たとえば、「先生がそんなことをするのか」「先生のくせに何やってんだ」という非難や批判は今に始まったことではない。そして、教員や警察官や自衛隊員による非行への処分は厳し...

コメント